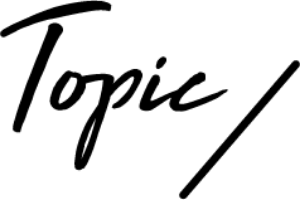お寺のブランドづくりから、
企業のブランドづくりへ。
“遺る”文化と価値をつくり続ける。
お寺のブランドづくりから、
企業のブランドづくりへ。
“遺る”文化と価値をつくり続ける。

2022年11月にdofに入社した宇佐見彰太。
大学卒業後、ファーストキャリアは総合商社。その後、MBAを取得し、スタートアップの取締役CFOを務めたのち、dofに参画するという異色の経歴の持ち主。そんな宇佐見が前職で深いつながりを持った世界遺産・仁和寺(真言宗御室派総本山)の管財課長 金崎義真さんとの対談をお届けします。全く違って見えるバックグラウンドの2人にとって、遺る文化をつくることとは?
2022年11月にdofに入社した宇佐見彰太。
大学卒業後、ファーストキャリアは総合商社。その後、MBAを取得し、スタートアップの取締役CFOを務めたのち、dofに参画するという異色の経歴の持ち主。そんな宇佐見が前職で深いつながりを持った世界遺産・仁和寺(真言宗御室派総本山)の管財課長 金崎義真さんとの対談をお届けします。全く違って見えるバックグラウンドの2人にとって、遺る文化をつくることとは?
元商社パーソン、世界遺産 仁和寺と出会う。
元商社パーソン、世界遺産 仁和寺と出会う。

ー 聞き手
今日はdofの宇佐見さんと、宇佐見さんが前職でお世話になった真言宗御室派 総本山仁和寺の金崎さんとの対談ということで、よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いします。
ー 宇佐見
宇佐見 彰太と申します。北海道札幌市出身です。総合商社、スタートアップのCFOを経由してdofにジョインしました。今日はよろしくお願いいたします。
ー 金崎さん
仁和寺の金崎です。よろしくお願いいたします。
私の仕事は、仁和寺の財産管理、管理と活用を担当するマネージャーと言うとわかりやすいかと思います。
ー 聞き手
金崎さんは、仁和寺に入られてどれくらいになるのでしょうか?
ー 金崎さん
10年とちょっとくらいですね。
ー 聞き手
仁和寺に入られる前は何をされていたんですか?
ー 金崎さん
仁和寺に入る前は、修行僧です。
ー 聞き手
宇佐見さんは総合商社では何をされていたのですか?
ー宇佐見
商社では世界中で発電事業や水事業、鉄道事業を扱うインフラ事業部門という部門の戦略企画や経営管理関連の仕事を担当していました。
ー 聞き手
その後、お寺関連のビジネスを創業したんですね。
ー 宇佐見
はい。商社の4年目からMBAに行かせてもらったのですが、そこで出会ったお寺出身で僧籍も持っている人と一緒に「お寺にまつわる社会課題解決」を目指す事業を始めました。
ー聞き手
現代のお寺には、どのような課題があるのでしょうか?
ー 金崎さん
お寺にはいろいろな役割がありますが、一般の方々から見ると大きく分けて「お墓と供養」と「観光資源」という面があるかと思います。特に前者は、これまでお檀家様に支えられて成り立ってきましたが、人口動態やライフスタイルの変化、人々の仏教離れの影響が顕著で、苦境に立たされているお寺も年々増えています。
ー 宇佐見
お寺の存続が危ぶまれる中、僕たちの会社も「お墓」と「観光」を二本柱として事業をつくっていました。「お墓」に関して言えば、「ユーザー」である一般の方々もお墓の継承や管理に関してさまざまなご不安を抱えていたので、立ち上げた事業では双方の課題に対処する「次世代型のお墓のプラットフォーム」の開発と、お墓そのものの建設、販売を行なっていました。
ー聞き手
つまり、お墓をつくって売っていたんですね。
ー 宇佐見
一言でいうとそうなりますね(笑)
ー 聞き手
二人はどういった事業がきっかけで出会ったのでしょうか?
ー 宇佐見
先ほどのお話にあった「お墓」と「観光」でいうと「観光」の方ですね。いわば「お寺のファンづくり」を支援する事業です。それを広げていく中で、真言宗の他派の方から「お寺の観光に関わるなら、金崎さんに会わないと」とご紹介をいただいたのが最初でした。
ー 金崎さん
そうですね。「よかったら、なんか実績を作ってあげてくれ」という話も込みで紹介をいただきました。

ー 聞き手
観光面では、どういったことが課題だったのですか?
ー 金崎さん
お寺に限った話ではないですが、コロナ禍に入って観光がストップしてしまったのが喫緊の課題でした。多くの方にお寺に来ていただいて仏教に親しんでほしいという想いもありますし、広大な敷地や文化財の管理という現実的な部分を考えても、お寺を訪れる方がいなくなってしまうのは大きな打撃です。
ー 宇佐見
神社仏閣について「参拝客97%減」などという衝撃的なニュースも流れていましたね。そんな中で、その後の段階的な観光客の回復を見越して、神社仏閣のファンづくりや地域経済の活性化を狙っていくべく、神社仏閣や行政と連携した取り組みをつくっていたのが「観光」の方の事業です。
ー 聞き手
最初はどんな提案をしたのでしょうか?
ー 宇佐見
当時は、人々が自宅から近いエリアで観光する「マイクロツーリズム」というトレンドが始まっていました。そういった中で、近郊の人々が繰り返しお寺を訪れて「仁和寺のファン」になってもらうための取り組みとして、季節ごとにデザインを変えた切り絵御朱印の頒布をご提案し、取り入れていただきました。切り絵の御朱印は今でも季節ごとにデザインを改めながら頒布を続けていただいています。

▲ 仁和寺の「切り絵御朱印」
▲ 仁和寺の「切り絵御朱印」
ー 聞き手
金崎さんは、そういった提案を持って来られて受ける機会は多いんですか?
ー 金崎さん
とても多いですね。そのときはお話を受けて、「切り絵の御朱印」がいいよねということですぐにスタートに向けて動き出しました。
ー 宇佐見
確かに、ものすごく早かったですね(笑)
すぐにデザインの取材に伺ったのを覚えています。
ー 聞き手
それにしても、宇佐見さんはその後dofにジョインした訳ですが、発電所からお墓と観光、そして今では広告やブランディングと、全然やっていることが違う感じがしますね。
ー 宇佐見
よくそう言われるのですが、僕の中では「ざっくり言うと同じ」という感覚があります。商材や組織の規模、立ち位置は違えど、共通しているのは「未来を見据えて企てる」ところから仕事が始まるということなので。
一千年を超える歴史に学ぶ。
「遺る価値づくり」のエッセンス。
一千年を超える歴史に学ぶ。
「遺る価値づくり」のエッセンス。

ー 聞き手
私も今日、仁和寺さんを見させていただいて、切り絵の御朱印も含め、新しい取り組みをたくさんされているんだなと感じました。仁和寺さんは888年から一千年以上続いているお寺で、「遺る価値をつくる」ということにどういったお考えをお持ちなのでしょうか。
ー 金崎さん
仁和寺ができたとき、仁和寺そのものが当時の最先端なんですよ。当時の最先端があって、そこから積み上げたものが1200年経って「歴史」になっています。なので、今の私たちとしてはこれから残っていくもの、先につながる可能性のあるものをやっていくべきだと考えています。そうなると、現代のものをいくらかは取り入れていかないと先につながらないのです。
ー 聞き手
お寺と聞くと、一般的には変えないことを是としているような風潮もあるのかなと思うのですが、いかがでしょうか?
ー 金崎さん
もちろんそういった見方が強いと思います。でも、お寺が「衰退している」とすれば、その「衰退」は結果でしかない。衰退に繋がっている「環境」を見逃しているから、結果的に「衰退」になっているはずなんですよ。業界内で、そのことに気づいてアプローチできる人が決して多くはないという課題もありますが、解決する方法が見つからないのは「環境」を紐解けていないところに原因があるんだと思います。
ー 宇佐見
ビジネスの世界で、「何を目指すのか」を考えるにあたって、そもそも今起こっていることの構造や、自分達を取り巻く環境をフラットに理解するのが重要だ、というのと同じですね。
ー 金崎さん
そうだと思います。そういう意味で、宇佐見さんはとても理路整然と環境を紐解いていたなと。だから、具体的な方法や手段が正しいかは別として、そのロジックでやっていけば「これはダメだったけどあれをやってみよう」と、いろいろな手を試していけます。それが決断が早かった理由でもありますね。

ー 宇佐見
金崎さんは、「古き良き伝統」を象徴するようなお寺にありながら、いろいろな現代のアーティストや若いクリエイターに活躍の場を提供されていますよね。それらの取り組みを見させていただく中で、今でこそ「伝統」と言われているものにもどこかに始まりがあるはずで、その種蒔きをして、お寺のあり方を少しずつアップデートしていくことが、後世につないでいく上で大事なのではないかと感じました。
ー 金崎さん
私はそもそも、お寺という場所は時代時代の最先端をいく場所だと思っています。芸術でも、寛平時代はこういう作風、鎌倉時代になるとこういう作風、といわれたりしますよね。俯瞰的に、年表で見たらそのように整理されるのですが、実際にはその間にもちょっとずつ変化しているんです。
ー 聞き手
一口に「伝統」と言っても一定のものではなかったということですね。
ー 金崎さん
そうですね。そしてその変化は今も続いているものだと思っています。だから「古ければいい」「昔のまま維持すればいい」ということではなくて、「今できることをやって、遺るものをつくらないといけないんじゃないですか?」という思いを持ちながらやっています。
ー 宇佐見
この考え方はビジネスにも通底すると思っていて、「つづく文化になること」は、ビジネスの言葉で言うと「サステナブル」そのものですよね。仁和寺で金崎さんをはじめいろいろな方とお仕事をさせていただく中での大きな気づきは、「遺る文化は現代にいる僕たちが創っていくいくものなんだ」ということ。さらに言えば、「ビジネスは文化になることでサステナブルになる」ということでした。
ー 聞き手
「遺る価値をつくる」というところで、仁和寺とdofの取り組みとが共通しているということですね。
ー宇佐見
本当に、そう思います。「文化と価値の創造」を掲げるdofとして、これまで「ハイボール」や「タクシーアプリGO」といった案件においては、ウイスキーやタクシーといったレガシーのある業界の中で新たな文化創造に挑戦してきました。伝統ある業界だからこそ、新たな種まきをすることがサステナブルに遺る文化になるために大事なことなのだと思います。
お寺とdofに共通点?
文化を創る企てに必要なものとは。
お寺とdofに共通点?
文化を創る企てに必要なものとは。

▲ インタビューの舞台は厨房と一緒に整備された「食堂(じきどう)」
▲ インタビューの舞台は厨房と一緒に整備された「食堂(じきどう)」
ー 聞き手
「遺る文化を創る」と言うところでdofの取り組みとお寺のあり方には共通点があることがわかりましたが、そのアプローチには何か共通する部分はあるのでしょうか?
ー 宇佐見
共通する部分があるとすれば、「遺るモノ(文化)になるためにはクリエイティブの力が不可欠」ということですね。
ー 聞き手
クリエイティブの力。
ー 宇佐見
象徴的な話としては、馬場康夫さんの『エンタメの夜明け』という本に書いてある、「厳島神社の鳥居」についての話があります。厳島神社の建立にあたって、一番最初に企画会議があったとして、あの鳥居を「海の中に建てようぜ」と言った人がいるはずであると。
ー 聞き手
神社建立の企画会議、という発想自体が面白いですが、確かに何かしらあったはずですよね。
ー 宇佐見
その「鳥居を海の中に建てる」というちょっとしたクリエイティビティがあったからこそ、今があるんだということです。1000年以上経った今、厳島神社はたくさんの人々の心を動かし、宮島という地域社会を支える観光資源になっていますし、日本全体で見ても多大な貢献をしています。ひとつのアイデア、少しのクリエイティビティがあったからこそ1000年、2000年遺るものになってきたということ。これは初期の仁和寺さんについても言えるのかなと思いますし、ビジネスが「文化」になることを考えたときにも、多くのレイヤーで言えることだと思います。
ー 聞き手
金崎さんは「クリエイティブの力が不可欠」、という話についてはどのように思われますか?
ー 金崎さん
100%必要でしょうね。仁和寺でも建立当初に限らず、その時代その時代の改修についても言えることだと思います。あるものをただ維持する、というところに目的意識が向いてしまうとクリエイティブではなくなってしまいますが、この先に遺っていくものを今つくることが将来へ繋いでいくことにつながると考えるのであれば、クリエイティビティは絶対に必要です。

▲ 仁和寺の厨房と「THE LEGENDARY JAPAN」当日の様子
▲ 仁和寺の厨房と「THE LEGENDARY JAPAN」当日の様子
ー 宇佐見
仁和寺を象徴する金堂や御殿、仁王門などに施されているさまざまな設えももちろん時のクリエイティブなのだと思いますが、今お話させていただいている部屋も現代的なデザインや技術とお寺という空間がうまく調和していますし、近年この部屋とセットで整備された厨房も仁和寺さんの新しい取り組みに繋がっていますよね。
ー 金崎さん
そうですね。元々は、文化財保全のために境内にある遊休資産をもっと活用できる形に変えていこう、という話をしていました。この場所も元々はただの蔵でしたし、境内の夜の時間も開放していませんでしたが、こうして宿泊できる形、活用できる形にすることで、文化に親しんでもらいながら、文化財保全のための財源確保の一助にもなる、という形を目指しました。余談ですが、このテーブルも実はお寺で使われていた古材を使って造ったものなんです。
ー 聞き手
利用する人はどのような形でここを使っているのですか?
ー 金崎さん
夜の境内を貸し切る、というところでは、料理を楽しむ人もいれば、パフォーマンスをする人もいれば、撮影する人もいる。いろいろな方に活用いただいています。
ー 宇佐見
僕も前職の2022年の5月に「THE LEGENDARY JAPAN」というプロジェクトを立ち上げて、実際にここの厨房などを使わせていただいたんですよ。
ー 聞き手
そうなんですね。どういったプロジェクトだったのでしょうか?
ー 宇佐見
コロナで落ち込んでいた日本の観光業を盛り上げよう、という目的で、「世界遺産の神社仏閣での文化体験」と「最高のシェフによる料理」を組み合わせたものでした。その初回を仁和寺さんで開催させていただきました。
ー 聞き手
どのようなコンセプトで取り組んだのでしょうか?
ー 宇佐見
先ほど金崎さんもおっしゃっていた、お寺は「お寺は古来より最先端の文化の交差点だった」ということをメタファーに、日本のいろいろな生産者さんの食材やお酒、陶芸作家さんの器、舞楽等の芸事も含めて、さまざまな文化が一堂に会して一つの時間、空間を作ることを目指しました。メゼババの髙山さんという本当に素晴らしいシェフに参加していただき当日の料理はもちろん、饗宴の体験をデザインしていただいたのも非常によかったですし、僕自身大変勉強になりました。ゆくゆくはこのプロジェクトが多くの生産者の方々や、職人の方々に多くを還元できるものに育って行くことを今も願っています。

ー 金崎さん
仁和寺としても厨房を整備したところで、ここで体験と食事を提供する、という形を模索していました。いろいろな試行錯誤をしていた中で、「できる限り質を高めたものをやってみる」ことの提案として受け取りました。
ー 宇佐見
dofでも、広告に限らず、場づくり、メディアづくり、イベントづくり、コンテンツづくり、時にはサービスそのものの設計といったところまで立ち返って課題解決のためのクリエイティブの力を求められる場面が増えていますが、実はお寺もそれと同じように場づくりやコトづくりに取り組んでいるということですね。
ー 聞き手
そう考えると意外な共通点ですね。
ー 宇佐見
そうですね。そして結果的にこのプロジェクトが「文化とビジネス、クリエイティブ」ということを深く考えるきっかけになり、そこでの出会いによって僕がdofにジョインすることに繋がっていったのも不思議なご縁だったなと思います。
永く続いていくブランドへ。
いざ、文化と価値の創造!
永く続いていくブランドへ。
いざ、文化と価値の創造!

ー 聞き手
一連の仁和寺さんとの取り組みやこれまでのキャリアを踏まえて、宇佐見さんがdofでどのようなことに取り組んでいきたいかを聞かせてください。
ー 宇佐見
まずは金崎さん、今日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。仁和寺さんと仕事をさせていただいたことは、とっても貴重な経験です。一千年以上続いているところに、ほんの一瞬の、小さなシミみたいな点でも関わらせていただくことなんてなかなかないですから。
その中で、僕自身のキャリアのテーマだった「ビジネスを通じた社会課題解決」や「サステナブル」という話と、「文化」や「クリエイティビティ」というものが交差したのは、仁和寺さんで仕事をさせてもらったからこその、僕にとって本当に宝物のような学びでした。
ー 金崎さん
次につながるものを得ていただいたなら何よりです。
ー 宇佐見
企業も仁和寺さんと同じで、自社のブランドやサービスが世の中の文化になることを目指すこともあれば、企業として「文化を創っていく」ことの一端を担うべく、次世代の文化の種蒔きをする立場に回ることもあります。
ー 聞き手
dofの取り組む案件でも、両方のパターンがありますね。
ー 宇佐見
はい。dofではどちらのパターンの仕事も担当させていただいているのですが、両方に共通した僕の想いとしては、長い目で見て「つづいていくもの」になっていくことにしっかりと伴走できたらいいな、ということです。
ー 聞き手
昨年のdof talkで紹介したカルチャーメディア『muda』も、クライアントがクリエイターと一緒になって文化を創り、発信していくプラットフォームを目指していると伺いました。
ー 宇佐見
まさにそうです。広告コミュニケーションではなかなか振り向いてくれない今の時代、「文化をつくる」という方向性で世の中に相対することは、遠回りに見えて実は正攻法だと思っています。頼りにしていただいた方と、一緒に未来の文化を企てていく。そんな心持ちで、楽しみながら進んでいけたらと思います。
ー 聞き手
最後に、金崎さんから宇佐見さんにメッセージをお願いします。
ー 金崎さん
先をみるロジックがしっかりしているので、そのまま、やりたいことに取り組んでいくのがいいと思いますよ。ちょっと無責任な言い方だけど、目指す方向、やっていることはきっと間違っていないから。できることがあれば、私はいつでも協力します、というスタンスですね(笑)
ー 宇佐見
本当にありがとうございます…!これからもよろしくお願いいたします。
金崎さん、ありがとうございました!

●構成・文:野崎 愉宇(dof)
●構成・文:野崎 愉宇(dof)

仲畑貴志が語る大島征夫。
仲畑貴志が語る大島征夫。
check this talk



一度限りの上場広告に
どう熱量を込めるか?
志の共鳴が生んだ
クリエイティブ誕生秘話
一度限りの上場広告に
どう熱量を込めるか?
志の共鳴が生んだ
クリエイティブ誕生秘話
check this talk



check this talk



弔辞を読んだ同志が語る、大島征夫。
弔辞を読んだ同志が語る、大島征夫。
check this talk